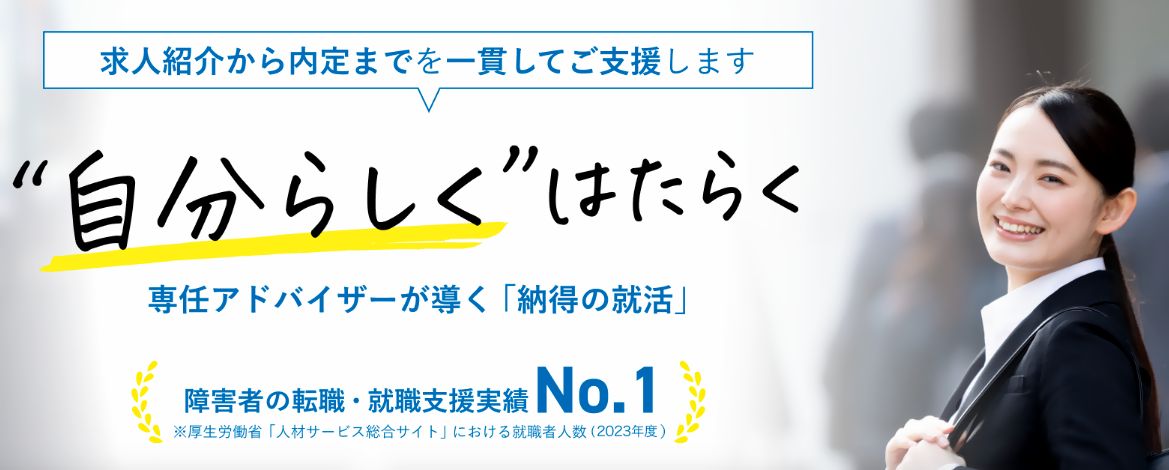dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や断られる人の特徴について解説します
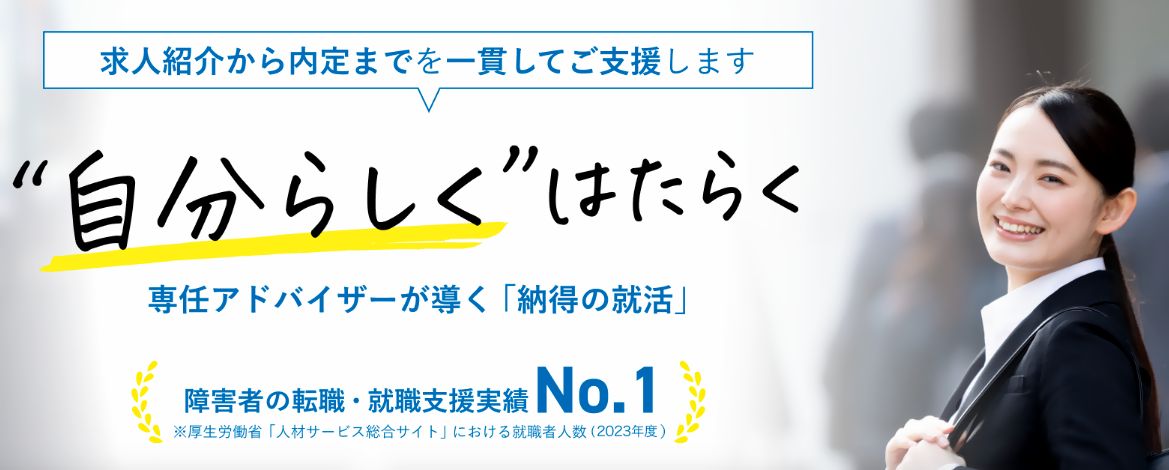
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
応募時に設定される希望条件が非常に高く設定されている場合、例えば完全な在宅勤務のみ、フルフレックス制限定、または年収500万円以上といった具体的かつ高額な条件を求めると、実際に市場に出回っている求人の数が非常に限られてしまいます。こうした条件は、企業側が提示する現実的な雇用条件と乖離していることが多く、エージェントがマッチングさせる求人案件が見つかりにくくなる原因となります。実際、企業は業績や経営戦略に基づいて現実的な条件を設定しているため、応募者が希望する水準と合致しない場合、断られる可能性が高くなります。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
特定の職種や業界にこだわりすぎると、求人市場の規模自体が狭まり、エージェントが紹介できる求人情報が非常に少なくなることがあります。例えば、クリエイティブ系やアート系の専門職は、求められるスキルや経験が非常に限定されるため、一般的な事務職や技術系職種と比べて求人の供給が少なくなりがちです。また、業界独自の資格や実績が必要な場合、応募者がその条件を十分に満たしていなければ、求人のマッチングが難しくなります。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
勤務地を特定の地域に限定してしまうと、特に地方では求人自体がもともと少ないため、エージェントが紹介できる求人案件が非常に限られてしまいます。都市部と比べると企業数が少なく、経済活動も縮小しているエリアでは、求人市場が狭いため希望の職種が出回る可能性が低くなります。地域の産業構造や人口動向なども影響し、結果として希望条件に合致する求人が見つかりにくくなるため、条件を柔軟に見直すことが求められます。
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
障がい者手帳を持っていない場合(障がい者雇用枠」での求人紹介は、原則手帳が必要)
障がい者雇用枠を活用する求人紹介の場合、制度上、障がい者手帳の所持が必須条件となるため、手帳を持たない状態で応募すると、エージェントはその応募者をサポート対象外と判断するケースが多いです。手帳は障がいの程度や必要な配慮事項を明確に示す重要な証明書として機能しており、これがない場合、企業側も安心して採用活動を行うことが難しくなります。手帳の取得は、就職支援を円滑に進めるための基本的な要件となっています。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
就職市場では、直近の職務経験や継続的な実績が評価の対象となるため、長期間のブランクがある、または短期間のアルバイトや派遣の経験しかない場合、エージェントは応募者のスキルや働く意欲について疑念を抱くことがあります。企業側は安定した業務遂行が可能であることを求めるため、ブランクが長い場合は、まずは就労移行支援や職業訓練を通じて、再び働ける状態に戻すことが推奨されます。これにより、将来的な就職のチャンスを広げることが可能となります。
状が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
精神的または身体的な状態が不安定な場合、企業は長期的な就労が可能かどうかを慎重に判断します。こうした状態が確認されると、エージェントは正規の求人紹介よりも、まずは就労移行支援などのサポートプログラムで安定した状況を作ることを優先するよう提案することが多いです。安定した健康状態と就労可能な環境が整えば、後に正規の求人紹介へとつながるため、初期段階での適切なサポートが重要となります。
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合
障がい内容や配慮事項が説明できない
面談の際に、応募者自身が自分の障がいや必要な配慮事項について明確に説明できないと、エージェントや企業側は適切なサポート方法を判断するのが難しくなります。具体的な事例や背景情報を十分に準備しておかないと、面談中に不明瞭な印象を与えてしまい、結果的に求人案件の紹介に支障が出る可能性があります。十分な事前準備と具体例の提示が求められます。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
面談時に、応募者がどのような仕事を希望しているか、そのキャリアビジョンが具体的でなければ、エージェントは応募者の将来性や意欲を判断するのが困難になります。明確な目標設定がないと、企業側も採用後の成長や長期的なキャリアプランを描きにくくなるため、自己分析を徹底し、自分の理想とする働き方やキャリアプランを具体的に伝えることが重要です。
職務経歴がうまく伝わらない
これまでの職務経歴や経験をうまく説明できない場合、応募者が持つスキルや実績が十分に伝わらず、企業側からの評価が低くなってしまいます。面談では、具体的な成果や取り組み内容、課題解決のエピソードなどを盛り込みながら、過去の実績を効果的にアピールすることで、応募者の能力を正確に伝えることが大切です。
断られる理由4・地方エリアやリモート希望で求人が少ない
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
特定の地方に居住している場合、特に北海道、東北、四国、九州など、主要都市から離れた地域では、求人情報自体が非常に少ない傾向があります。地域ごとの経済規模や企業数の違いから、地方在住の応募者は都市部に比べて就職のチャンスが狭まるため、エージェントが紹介できる求人が限定されやすいという現実があります。地域特有の就職支援策を利用することも検討すべきです。
完全在宅勤務のみを希望している場合(dodaチャレンジは全国対応ではあるが地方によっては求人がかなり限定される)
完全な在宅勤務を希望する場合、エージェントが提供する求人の中からその条件を満たすものを探し出すのは非常に困難です。dodaチャレンジは全国対応ですが、特に地方では在宅勤務の求人が少ないため、希望条件が厳しくなると求人のマッチングが成立しにくくなります。条件の見直しや、柔軟な働き方の選択肢を検討することで、より多くの求人に出会う可能性が高まります。
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
登録情報に実際と異なる内容を記載してしまうと、後にエージェントや企業からの信頼を失う原因となります。例えば、実際には障がい者手帳を持っていないにもかかわらず「取得済み」と記載してしまうと、面接時や採用後に問題が発覚し、信頼性の低下につながります。正確な情報提供が、応募者自身の信用を高めるために非常に重要です。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
自身の健康状態や就労可能性に見合わない状況で登録を行うと、エージェントは実際の採用に向けたサポートが難しいと判断します。現実の就労可能性を正確に反映した情報を登録することで、適切な求人の紹介や、必要な支援を受けるための基礎が整います。自己評価と現実の状況をしっかりと見極めることが重要です。
職歴や経歴に偽りがある場合
職務経歴や資格、実績に虚偽の情報を含めると、採用プロセスで後々問題が発覚するリスクが高まります。エージェントは応募者の情報の信頼性を重視するため、虚偽が発覚すれば求人紹介が完全に停止される可能性もあります。正直かつ詳細な情報提供が、円滑な就職活動を進めるための基本です。
断られる理由6・企業側から断られるケースも「dodaチャレンジで断られた」と感じる
不採用は企業の選考基準によるもの
求人紹介がうまくいかない場合、エージェントの努力だけではなく、企業側の独自の選考基準や採用ポリシーが大きく影響していることもあります。応募者のスキルや経験が企業の求める条件に合致しなかった場合、エージェント側の紹介努力に関わらず、不採用となる可能性が高くなります。企業の採用基準は各社で異なり、様々な要因が影響するため、断られたと感じる場合でも、個人の能力やサービス自体を否定するものではありません。
dodaチャレンジ

dodaチャレンジで断られた人の体験談/どうして断られたのか口コミや体験談を調査しました
体験談1・障がい者手帳は持っていましたが、これまでの職歴は軽作業の派遣だけ。PCスキルもタイピング程度しかなく、特に資格もありません。紹介できる求人がないと言われてしまいました
ある応募者は、障がい者手帳を所持していたものの、これまでの職歴が軽作業の派遣業務のみであったため、専門的なスキルや資格が不足していると判断され、エージェントからは紹介可能な求人が見つからないと回答されました。この体験談は、職務経験の多様性やスキルアップの必要性を強く示唆しており、今後のキャリア形成においては資格取得や実務経験の積み重ねが求められるといえます。
体験談2・継続就労できる状態が確認できないため、まずは就労移行支援などで安定した就労訓練を』と言われてしまいました。
ある応募者は、就労の継続性に不安があると判断され、正規雇用の求人紹介につながる前に、まずは就労移行支援施設での訓練や実践的な就労体験を勧められました。これにより、就業環境に慣れ、安定した就労実績を積むためのステップとして、再度サービス利用に繋げるための基盤作りが提案されました。
体験談3・精神疾患で長期療養していたため、10年以上のブランクがありました。
精神疾患により長期間療養していた応募者は、10年以上の職務ブランクがあることから、dodaチャレンジに相談した際に「ブランクが長く、直近の就労経験がないため、まずは体調の安定と職業訓練を優先するべき」というアドバイスを受けました。この事例は、健康管理の重要性と、ブランク解消のための段階的なキャリア復帰が必要であることを示しています。
体験談4・四国の田舎町に住んでいて、製造や軽作業ではなく、在宅でのライターやデザインの仕事を希望していました。dodaチャレンジからは『ご希望に沿う求人はご紹介できません』といわれました
四国の過疎地域に住む応募者は、製造や軽作業ではなく在宅でのクリエイティブな仕事を希望していました。しかし、地域の求人状況やエージェントの求人データの現状から、希望条件に合致する案件が見つからず、最終的に「ご希望に沿う求人はご紹介できません」と断られたという体験がありました。地域特性や求人の少なさが、希望職種とのミスマッチにつながる例と言えるでしょう。
体験談5・これまでアルバイトや短期派遣での経験ばかりで、正社員経験はゼロ。
アルバイトや短期派遣中心の職歴しか持たなかった応募者は、正社員としての採用実績が全くなく、dodaチャレンジに登録した際に「現時点では正社員求人の紹介は難しい」という回答を受けました。この事例は、正社員としての実績や安定性が評価の対象となるため、まずは実務経験を積むことの重要性を示唆しています。
体験談6・子育て中なので、完全在宅で週3勤務、時短勤務、かつ事務職で年収300万円以上という条件を出しました。『ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しいです』と言われ、紹介を断られました
子育てと仕事の両立を希望し、完全在宅勤務で週3日、時短勤務、さらに事務職で年収300万円以上という複数の条件を同時に提示した応募者は、条件の厳しさからエージェントがすべての希望を同時に叶える求人を見つけられず、断られてしまいました。条件の優先順位を見直す必要性が改めて浮き彫りとなった事例です。
体験談7・精神障がい(うつ病)の診断を受けていますが、障がい者手帳はまだ取得していませんでした。dodaチャレンジに登録を試みたところ、『障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しい』と言われました
精神障がいの診断を受けながらも、障がい者手帳を未取得であったため、応募者はdodaチャレンジのサポート対象外と判断され、求人紹介が難しいと回答されました。この体験談は、手帳の取得が雇用支援制度においていかに重要な役割を果たすかを示しており、早期の手帳取得が推奨される理由を物語っています。
体験談8・長年、軽作業をしてきたけど、体調を考えて在宅のITエンジニア職に挑戦したいと思い、dodaチャレンジに相談しました。『未経験からエンジニア職はご紹介が難しいです』と言われ、求人は紹介されませんでした
これまで軽作業に従事していた応募者が、体調面やライフスタイルの変化を踏まえて在宅勤務のITエンジニア職にキャリアチェンジを希望しましたが、全くの未経験であったために、エージェントからは適切な求人案件の紹介が難しいと判断されました。キャリアチェンジには段階的なスキルアップや専門的な研修が必要であるという現実を反映した体験です。
体験談9・身体障がいで通勤も困難な状況で、週5フルタイムは無理。短時間の在宅勤務を希望しましたが、『現在ご紹介できる求人がありません』と断られました
身体障がいにより通勤が難しい応募者は、週5フルタイムではなく短時間の在宅勤務を希望したものの、実際の求人市場ではその条件に合致する案件が見つからなかったといいます。障がいの内容や勤務可能な時間帯の制約が、求人の選択肢を大きく狭める原因となっている例です。実際の就業環境に合わせた柔軟な働き方の提案が求められます。
体験談10・前職は中堅企業の一般職だったけど、今回は障がい者雇用で管理職や年収600万以上を希望しました。dodaチャレンジでは『ご紹介可能な求人は現在ありません』と言われました
中堅企業での一般職としての経歴を持つ応募者が、障がい者雇用枠を利用して管理職や高年収(600万円以上)のポジションを狙った結果、現実的にはそのような高条件の求人が市場にほとんど存在しないため、「ご紹介可能な求人は現在ありません」と断られた事例です。応募条件と市場の実情との乖離が、今回の断りの原因として大きく影響していると考えられます。
dodaチャレンジ

dodaチャレンジで断られたときの対処法について詳しく紹介します
スキル不足・職歴不足で断られたとき(職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がないなど)の対処法について
ハローワークの職業訓練を利用する/ 無料または低額でPCスキル(Word・Excel・データ入力など)が学べる
ハローワークが提供する職業訓練プログラムは、受講料が無料または低額である上、基本的なPCスキルやデータ入力技術を短期間で習得することができるため、就職活動の基礎力向上に大いに役立ちます。こうした訓練を受けることで、業界で求められる基本スキルの習得だけでなく、職場での実践的な業務に対応できる自信を養うことができ、応募時に有利な材料となります。
就労移行支援を活用する/実践的なビジネススキル、ビジネスマナー、メンタルサポートも受けられる
就労移行支援プログラムでは、実際のビジネス現場を想定したトレーニングが受けられ、ビジネスマナーやコミュニケーションスキルの向上、さらにはメンタル面でのサポートが提供されます。これにより、応募者は単にスキルを学ぶだけでなく、社会で必要とされる総合的な能力を身につけることができ、面接時や実務での自信につながるため、就職成功の確率が高まります。
資格を取る/MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級があると、求人紹介の幅が広がる
資格取得は、応募者が業務に必要な能力を客観的に証明する手段として有効です。例えば、MOSや日商簿記3級のような資格は、基礎的な業務スキルの習得を証明するだけでなく、企業側に対して信頼性の高いアピールポイントとなります。資格があれば、求人の選択肢が広がり、企業にとっても採用リスクが低減されるため、積極的に資格取得を目指すことが推奨されます。
ブランクが長すぎてサポート対象外になったとき(働くことへの不安が強い、数年以上の離職や療養機関があるなど)の対処法について
就労移行支援を利用して就労訓練をする/毎日通所することで生活リズムを整え、安定した就労実績を作れる
長期のブランクがある場合、就労移行支援施設での定期的な訓練は、生活リズムの再構築と就労可能な状態への復帰に非常に効果的です。毎日の通所や業務体験を通じて、実際の職場環境に慣れると同時に、企業側に対して継続的な就労実績として評価される証拠を作ることができます。これにより、ブランクがあっても再就職のチャンスが高まります。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る/週1〜2の短時間勤務から始めて、「継続勤務できる」証明をつくる
いきなりフルタイムの正社員求人に挑戦するのではなく、まずは短時間のアルバイトや在宅ワークで働く実績を作る方法も効果的です。週1〜2日の勤務から始め、徐々に勤務時間を延ばすことで、企業に対して「継続して勤務できる」という信頼感を示すことが可能となります。実績の積み重ねが、後の正社員採用へとつながる重要なステップとなります。
実習やトライアル雇用に参加する/企業実習での実績を積むと、再登録時にアピール材料になる
企業での実習やトライアル雇用に参加することで、実際の業務を体験しながら具体的な実績を積むことができます。こうした実習経験は、エージェントへの再登録時に応募者の強みとして大きくアピールでき、正社員としての採用チャンスを広げるための有効な材料となります。実際の業務環境での経験は、自己成長にも大いに寄与します。
地方在住で求人紹介がなかったとき(通勤できる距離に求人が少ない、フルリモート勤務を希望しているなど)の対処法について
在宅勤務OKの求人を探す/他の障がい者専門エージェント(atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレ)を併用
地方在住の場合、通勤可能な範囲に十分な求人が存在しないことが多いため、在宅勤務可能な求人に目を向けることが有効です。dodaチャレンジだけでなく、atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレなど、複数の障がい者専門エージェントを併用することで、より広範な求人情報にアクセスすることが可能となります。地域に縛られない働き方を模索することが、就職成功への一歩となります。
クラウドソーシングで実績を作る/ランサーズ、クラウドワークスなどでライティングやデータ入力の仕事を開始
クラウドソーシングのプラットフォームを利用して、ライティング、データ入力などの在宅ワークで実績を積むことも有効な手段です。オンライン上での実績や評価が蓄積されることで、企業側に対して自身の働く姿勢や能力を証明することができ、将来的により大きなプロジェクトや正社員採用への道が開かれる可能性があります。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談する/地元密着型の求人情報が得られる場合がある
地方では、地域に根ざした障がい者就労支援センターやハローワークが、地元企業との強固なネットワークを持っていることが多く、全国的な求人情報とは一味違った求人案件を紹介してくれる場合があります。こうした公的な窓口に直接相談することで、地域の特性に合った求人情報を得るチャンスが増えるため、積極的に活用することが望まれます。
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について
条件に優先順位をつける/「絶対譲れない条件」と「できれば希望」を切り分ける
複数の希望条件を同時に提示すると、企業側が応えられる求人が極端に少なくなります。そのため、まずは「絶対に譲れない条件」と「可能であれば希望する条件」に分け、優先順位を明確にすることが重要です。条件を整理することで、柔軟な交渉が可能となり、現実的な求人とのマッチング率が向上します。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する/ 勤務時間、出社頻度、勤務地を柔軟に見直す
面談時にエージェントと具体的な条件について話し合い、譲歩可能な項目については再度提示することが大切です。例えば、勤務時間の調整や出社頻度、勤務地の範囲を柔軟に見直すことで、企業側の採用基準に合わせた求人が見つかる可能性が高まります。現実の求人市場とのバランスを取ることが、最終的なマッチング成功に寄与します。
段階的にキャリアアップする戦略を立てる/最初は条件を緩めてスタート→スキルUPして理想の働き方を目指す
いきなり全ての希望条件を満たす求人を求めるのではなく、まずは現実的な条件でスタートし、仕事を通じてスキルや経験を積むことで段階的にキャリアアップしていく戦略が有効です。短期的な目標と長期的なビジョンを設定し、経験を積むことによって、将来的には理想の条件に近い求人に応募する準備が整うため、焦らずに計画的に進めることが求められます。
手帳未取得・障がい区分で断られたとき(障がい者手帳がない、精神障がいや発達障がいで手帳取得が難航している、支援区分が違うなど)の対処法について
主治医や自治体に手帳申請を相談する/ 精神障がい・発達障がいも条件が合えば取得できる
手帳が未取得の場合、まずは主治医や自治体の福祉担当窓口に相談し、障がい者手帳の取得手続きについて詳しい情報を得ることが大切です。状況に応じて、精神障がいや発達障がいでも必要な条件を満たせば手帳が交付されるケースがあるため、早期の申請が推奨されます。正確な情報をもとに、適切な手続きと準備を進めることが重要です。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK求人」を探す/一般枠での就職活動や、就労移行後にdodaチャレンジに戻る
手帳を持っていない場合でも、就労移行支援やハローワークなどでは、障がい者手帳が必須でない一般雇用枠の求人が存在する場合があります。こうした求人を通じて実績を積み、後に手帳を取得してからdodaチャレンジに再登録するという戦略も有効です。段階的なキャリア形成を意識し、柔軟に対応することが就職成功の鍵となります。
医師と相談して、体調管理や治療を優先する/手帳取得後に再度登録・相談する
体調や治療の状況が優先される場合、まずは医師としっかり相談し、健康状態の安定を図ることが最優先です。体調が整い、手帳取得が可能な状態になった段階で再度登録や相談を行えば、より具体的な求人紹介が受けられる可能性が高まります。自身の健康を第一に考えた上で、将来的な就労に向けた準備を進めることが望まれます。
その他の対処法/dodaチャレンジ以外のサービスを利用する
上記の対処法以外にも、dodaチャレンジ以外の就職支援サービスや障がい者向けのエージェントを併用することで、より多くの求人情報にアクセスすることができます。複数の支援窓口やサービスを活用することで、個々の状況に合わせた柔軟なサポートが受けられ、最適な就職先に出会える可能性が広がります。各サービスの特徴を十分に理解した上で、自分に合った支援を選択することが重要です。
dodaチャレンジ

dodaチャレンジで断られた!?精神障害や発達障害だと紹介は難しいのかについて解説します
身体障害者手帳の人の就職事情について
障害の等級が低い場合は就職がしやすい
身体障害者手帳をお持ちの場合、障害の程度が軽度または中度であれば、企業側が必要な配慮をしやすく、一般的な職種への採用が進みやすい傾向があります。実際の職場では、具体的な配慮策が明確に示されることで、業務上の支障が少なく、応募者としての魅力が高まるため、就職がスムーズに進むケースが多く見られます。
身体障がいのある人は、障がいの内容が「見えやすい」ことから、企業側も配慮しやすく採用しやすい傾向にある
目に見える障がいの場合、企業側は必要な配慮や合理的な措置を事前に計画しやすいため、安心して採用を進めることができます。障がいの程度や具体的な配慮内容が把握しやすいため、企業は面接や採用後のサポート体制を整えやすく、採用率が上がる傾向にあります。実際、物理的な障害の場合、対策としてオフィスのバリアフリー化や業務内容の調整などがすぐに実施されることが多いです。
企業側が合理的配慮が明確にしやすい(例:バリアフリー化、業務制限など)から、企業も安心して採用できる
企業が具体的な合理的配慮策を提示できる場合、採用後の不安が軽減され、安心して応募者を迎えることができます。たとえば、オフィスのバリアフリー化や作業内容の一部調整など、事前に対応策を明確にしておくことで、企業は採用に踏み切りやすくなり、結果として就職がしやすくなります。
上肢・下肢の障がいで通勤・作業に制約があると求人が限られる
上肢や下肢に障がいがある場合、通勤方法や作業内容に制約が出るため、求人の選択肢が限られてしまうことがあります。企業側もその点を考慮し、業務内容を調整する必要があるため、条件に合致する求人が少なくなる傾向が見られます。こうした状況では、事前に必要な配慮事項をしっかりと伝えることで、企業との調整がスムーズに進む場合もあります。
コミュニケーションに問題がない場合は一般職種への採用も多い
身体障がいがあっても、コミュニケーション能力に自信がある場合、企業側はその能力を重視して一般職種や事務職など、コミュニケーションが中心の業務に採用する傾向があります。面接や実務試験でその能力が十分にアピールできれば、障がいがあっても十分な採用の可能性があります。
PC業務・事務職は特に求人が多い
実際、PCを使用した業務や事務職は、企業にとっても必要不可欠な業務であるため、障がいの有無にかかわらず、求人件数が豊富です。こうした職種は、業務内容が明確であり、必要な配慮も具体的に定めやすいため、応募者にとっても採用されやすい環境が整っています。
精神障害者保健福祉手帳の人の就職事情について
症状の安定性や職場での継続勤務のしやすさが重視される
精神障害者保健福祉手帳を持つ方の場合、企業側は症状の安定性と、長期にわたって勤務できるかどうかを重視します。就職前に十分な治療やカウンセリングを受け、安定した状態であることが評価されるため、安定した環境づくりが不可欠となります。面接時には、現在の状況や治療の進捗状況を正直に伝えることが重要です。
見えにくい障がいなので、企業が「採用後の対応」に不安を持ちやすいのが現実
精神障害の場合、その症状が外見からは分かりにくいため、企業側が採用後のサポート体制や働き方について不安を感じることが少なくありません。こうした不安を解消するためには、面接の際に具体的なサポート策や自分自身の対策について説明し、企業に安心感を与えることが大切です。
採用面接での配慮事項の伝え方がとても大切!
精神障害者の場合、採用面接でどのような配慮が必要かを明確に伝えることが、採用後の円滑な就業に直結します。事前に自分の状況や必要な支援について整理し、具体的な例を交えて説明することで、企業は安心して採用活動を進めることができるようになります。面接準備を十分に行うことが成功のカギとなります。
療育手帳(知的障害者手帳)の人の就職事情について
療育手帳の区分(A判定 or B判定)によって、就労の選択肢が変わる
知的障害者手帳の場合、A判定とB判定という区分により、就労できる職種や業務内容が大きく異なります。各判定に応じた支援策や就労環境が整っており、応募者は自分に最も適した働き方を選択することが求められます。制度の内容を十分に理解し、自身の状況に合わせた就労プランを立てることが重要です。
A判定(重度)の場合、一般就労は難しく、福祉的就労(就労継続支援B型)が中心
A判定に該当する場合、重度の障がいがあるため、通常の企業での一般就労は困難となり、福祉的な就労支援が中心となります。こうした環境では、特別な支援体制や企業との調整が必要となるため、専門の就労支援機関と連携しながら、現実的な就労プランを策定することが不可欠です。
B判定(中軽度)の場合、一般就労も視野に入りやすい
B判定の場合は、重度ではないため、企業での一般就労も十分に視野に入ります。必要なサポート体制が整えば、通常の就労環境で働くことが可能となり、応募者の能力に応じた幅広い職種へのチャレンジが可能です。自分の強みを活かせる職種を見つけるための情報収集が大切です。
障害の種類と就職難易度について
| 手帳の種類 |
就職のしやすさ |
就職しやすい職種 |
難易度のポイント |
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) |
★★★★★★ |
一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート |
配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) |
★★ |
軽作業・在宅勤務 |
通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 |
★★ |
事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク |
症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) |
★★★★ |
軽作業・事務補助・福祉施設内作業 |
指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) |
★★ |
福祉的就労(A型・B型) |
一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いについて
障害者雇用枠の特徴1・企業が法律に基づき設定している雇用枠
障害者雇用枠は、法律に則った形で企業が必ず一定割合の障がい者を雇用するために設けられた制度です。この枠組みにより、企業は採用活動において障がい者の雇用を促進する義務があり、そのための制度的な支援が行われています。企業も制度上のメリットを享受しながら採用活動を進めることができるため、比較的安定した求人が存在します。
障害者雇用枠の特徴2・障害者雇用促進法により、民間企業は従業員の2.5%以上(2024年4月〜引き上げ)を障がい者として雇用するルールがある
障害者雇用促進法の改正により、民間企業は従業員全体の一定割合(2024年4月以降は2.5%以上)を障がい者として雇用することが義務付けられています。これにより、企業は積極的な採用活動を進めざるを得なくなり、障がい者の就職機会が増加する仕組みが整備されています。企業側も法令遵守の観点から、この枠を活用して採用を行う傾向があります。
障害者雇用枠の特徴3・障害をオープンにし配慮事項を明確に伝えた上で雇用される
この枠では、応募者自身が障がいの内容や必要な配慮事項を明確に伝えることが求められます。企業側はこれをもとに、合理的な配慮を行いながら業務に支障が出ないように採用プロセスを進めるため、採用後の環境整備がスムーズになります。双方の透明性が確保されることで、安心して働くことが可能となります。
一般雇用枠の特徴1・障害の有無を問わず、すべての応募者が同じ土俵で競う採用枠
一般雇用枠は、障がいの有無にかかわらずすべての応募者が平等な条件で競争する枠となっており、特別な配慮措置が講じられないのが前提です。このため、応募者は純粋に自身のスキルや経験を基に評価されるため、障がいがあってもない場合と同様に、通常の就職活動と同じプロセスを経ることになります。
一般雇用枠の特徴2・障害を開示するかは本人の自由(オープン就労 or クローズ就労)
この枠では、応募者が自分の障がい情報を開示するかどうかは本人の自由とされ、採用プロセスにおいてその選択が尊重されます。開示することで合理的な配慮を企業に求めることもでき、開示しない場合は通常の採用選考が行われるため、応募者は自分の状況に応じた働き方を選択することが可能です。
一般雇用枠の特徴3・基本的に配慮や特別な措置はないのが前提
一般雇用枠では、採用プロセスにおいて特別な配慮や措置が設けられていないため、全応募者が同一の採用基準で評価されます。このため、障がいがある場合でも、応募者は通常の選考プロセスを経る必要があり、企業側もその基準に従って採用判断を行います。
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか
障害者雇用状況報告(2023年版)を元に紹介します
| 年代 |
割合(障害者全体の構成比) |
主な就業状況 |
| 20代 |
約20~25% |
初めての就職 or 転職が中心。未経験OKの求人も多い |
| 30代 |
約25~30% |
安定就労を目指す転職が多い。経験者採用が増える |
| 40代 |
約20~25% |
職歴次第で幅が広がるが、未経験は厳しめ |
| 50代 |
約10~15% |
雇用枠は減るが、特定業務や経験者枠で採用あり |
| 60代 |
約5% |
嘱託・再雇用・短時間勤務が中心 |
若年層(20〜30代)の雇用率は高く、求人数も多い
20代から30代の応募者は、比較的若いため、未経験でも企業側がチャレンジしやすく、また多くの求人が用意されているため、就職しやすい傾向にあります。若年層は柔軟性が高く、成長意欲が強いと評価され、企業も積極的に採用に動くケースが多く見受けられます。
40代以降は「スキル・経験」がないと厳しくなる
40代以上になると、これまでの職務経験や専門スキルがより一層重視されるため、未経験の場合は求人の選考が厳しくなる傾向があります。経験や実績があることが前提となるため、必要なスキルアップや自己研鑽が求められ、企業側の評価も厳しくなるケースが多いです。
50代以上は「短時間勤務」「特定業務」などに限られることが多い
50代以上の応募者は、体力や健康面、または企業側のニーズに合わせ、短時間勤務や特定の業務に限定される傾向があります。これにより、求人の選択肢が狭まる可能性があり、応募する際にはそれに応じた対策や準備が必要となります。年齢層に合わせた柔軟な働き方が求められる時代となっています。
dodaチャレンジなどの就活エージェントのサービスに年齢制限はある?
年齢制限はないが 実質的には「50代前半まで」がメインターゲット層
公式上は年齢制限が設けられていないものの、実際にdodaチャレンジが主にサポートしているのは、50代前半までの応募者です。これは、企業側が求めるスキルや経験、さらには体力面などの条件と照らし合わせた結果であり、実質的なターゲット層が決まっているといえます。応募者は自身のキャリアプランに合わせて、どのサービスが最適かを検討する必要があります。
ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)も併用するとよい
dodaチャレンジの利用が難しい場合でも、ハローワークの障がい者窓口や独立行政法人が運営する障がい者職業センターなど、他の公的な支援窓口と併用することで、より多くの求人情報にアクセスできる可能性が広がります。これにより、地域ごとの求人状況に応じたサポートが受けられ、就職活動の幅が大きく広がります。
dodaチャレンジ

dodaチャレンジの口コミはどう?についてよくある質問
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
実際の利用者から寄せられる口コミや評判は、dodaチャレンジの実情を知るための貴重な情報源となっています。利用者の体験談や評価を通じ、どのようなサポートが提供されるのか、またサービスの強みや改善点が明らかになっており、今後の就職活動に活かすためのヒントが多く含まれています。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
求人で断られてしまった場合、まずは自分のスキルや希望条件を再評価し、必要に応じて条件の見直しやスキルアップを図ることが大切です。エージェントと具体的な対策を相談しながら、次に備える準備を着実に進めることが成功への近道となります。
関連ページ:dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
面談後に連絡がない場合、企業側の採用判断や内部の調整状況、またはエージェント側の案件の状況が影響している可能性があります。応募者は、事前に確認やフォローアップの手段を講じることで、次のステップに備えるための情報を得ることができます。
関連ページ:dodaチャレンジから連絡なしの理由と対処法/面談・求人・内定それぞれのケースと連絡なしの理由
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
面談では、これまでの職歴、障がいの状況、希望する働き方など、多角的な情報が求められます。十分な事前準備と自己分析が必要であり、具体的なエピソードを交えながら、企業側に自身の強みや必要な支援について正確に伝えることが重要です。
関連ページ:dodaチャレンジの面談から内定までの流れは?面談までの準備や注意点・対策について
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がいを持つ方々に特化した就職支援サービスとして、個々の状況や希望に応じた求人の紹介、面談を通じたキャリアカウンセリング、さらには各種支援プログラムの案内など、多岐にわたるサポートを提供しています。利用者一人ひとりに対して柔軟な対応を行い、安心して就職活動が進められるように配慮されている点が特徴です。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
原則として、障がい者雇用枠を利用した求人紹介には障がい者手帳が必要となるため、手帳を未取得の場合は利用が難しいとされています。しかし、一般雇用枠での就職支援や、就労移行支援を利用することで、別の形でサポートを受ける方法も検討可能です。
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
基本的にはすべての障がいを対象としていますが、制度上の要件や個別の状況によっては、登録や求人紹介が難しいケースも存在します。具体的な状況に応じた相談を行い、最適なサポート方法を見つけることが推奨されます。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
退会や登録解除の手続きは、公式サイト上の案内や担当者からの説明に基づいて行われます。手続き自体はシンプルですが、今後の就職活動への影響を十分に考慮した上で進めることが重要です。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
キャリアカウンセリングは、dodaチャレンジの各拠点やオンラインを通じて受けることが可能です。面談形式で行われるため、事前の予約や問い合わせを行い、最寄りの窓口や対応可能な日時を確認することが推奨されます。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
公式上は年齢制限は設けられていませんが、実際には主に50代前半までの応募者が対象となるケースが多く、年齢が上がるにつれて求人の内容や求められる経験が変わるため、エージェント側のマッチングにも影響が出ることが考えられます。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
離職中でも、就労可能な状況やスキルに応じたサポートを受けることは可能です。ただし、離職期間やブランクの状況によっては、まずは就労移行支援などを通じた訓練やサポートが勧められるケースもあります。自身の現状を正確に把握し、エージェントと相談しながら次のステップを模索することが大切です。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
学生の方でも利用は可能ですが、就労形態がアルバイトやインターンシップなど異なるため、個別にサポート内容が異なる場合があります。将来の就職活動に向けたキャリア形成の一環として、学生向けの支援プログラムやアドバイスが受けられるため、積極的に相談することが推奨されます。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)